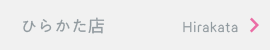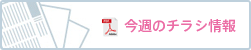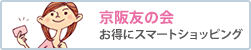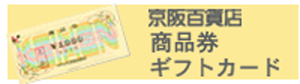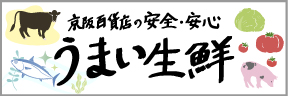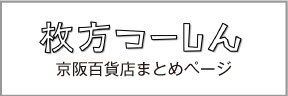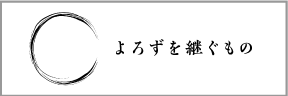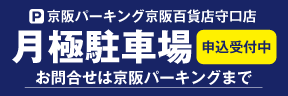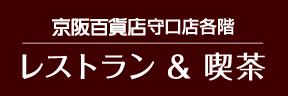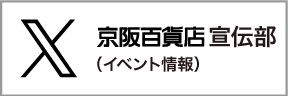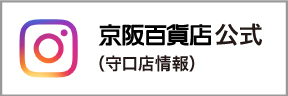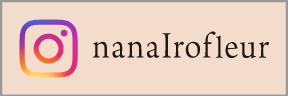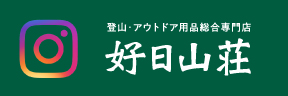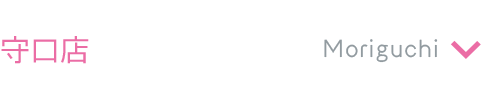2025年(令和7年)6月 水無月
芒種 6月5日から 稲や麦など穂のなる穀物の種を蒔くころ
夏至 6月21日から 一年で最も日が出ている時間が長い日
衣替え

最近は暑くなる時期も早まってきているので、もう既に衣替えを済ませたという方も多いかもしれませんが、
古くからの風習では衣替えは6月1日と10月1日とされていました。
旧暦の4月と10月に中国の宮廷で春と秋に夏服と冬服を入れ替えていたことから始まった風習で、
日本では平安時代に宮中行事として取り入れられたそうです。
当初は貴族だけの行事で、年に2回だけでしたが、
江戸時代になると、幕府によって年に4回衣替えをすると武家の規則として取り決められたようです。
当初は武家だけの規則でしたが、徐々に一般庶民にも浸透し、風習として広まっていきました。
この風習は和服の世界では今でも重要視されているようです。
梅雨のじめじめでお洗濯が思い通りにいかないこともありますが、
お天気のタイミングを見計らいながら衣替えで気分転換するのはいかがでしょうか。
梅仕事

6月といえば真っ先に思いつくのが梅雨。
梅雨入りと似た言葉で、「入梅」があります。
季節の移り変わりを把握するための暦である雑節で、太陽の黄経が80度に達した日をさします。
以前は立春から数えて135日目、さらに昔の暦では「芒種」のあとの最初の「壬(みずのえ)の日」とされていました。
雑節の入梅は、実際の梅雨入りとは異なりますが、農作業の目安として重要視されてきました。
「梅」という文字が使われているとおり、この時季は梅の実が実る時季です。
梅酒を漬けたり、梅干しを作ったりすることを「梅仕事」といいますが、
昔から梅は「三毒(食べものの毒・血液の毒・水の毒)」を断つといわれる健康食とされており、
この時季の梅仕事は人々にとって欠かせないものだったようです。
楽しく美味しい季節の手仕事。未体験の方も今年は自家製の梅酒や梅シロップ、梅干しづくりに挑戦してみませんか?
- 売場
- 5F
- 守口店
- くずはモール店
- ひらかた店
- モール京橋店
- すみのどう店